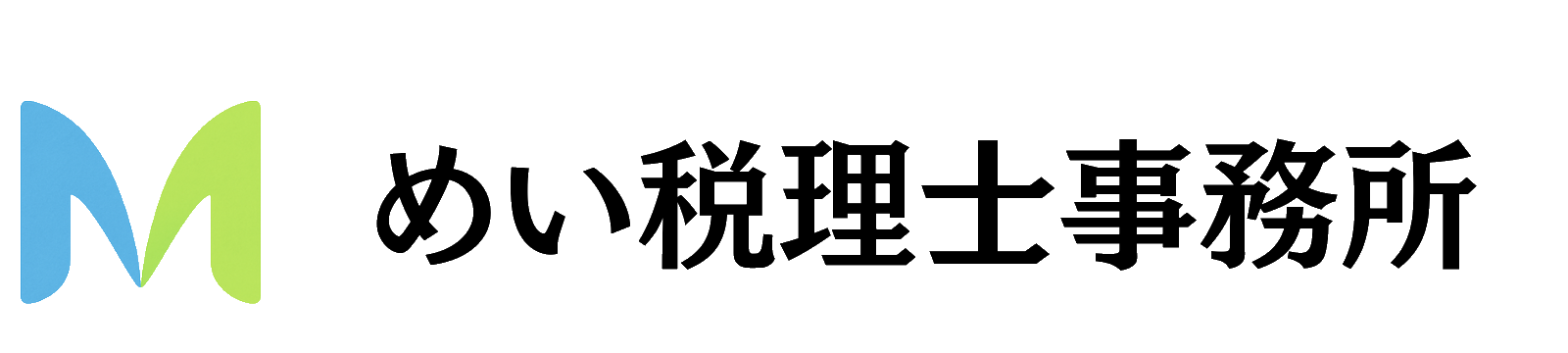Site Menu
相続税評価のルールは変わった?─総則6項と令和4年最高裁判決の意義を読み解く
こんにちは。千代田区水道橋の税理士の竹岡悟郎です。今回は近年いろいろ話題になっている、いわゆる「総則6項」について簡単に(簡単ではないですが・・・)お伝えしたいと思います。
相続税の世界では、「評価のルールに従って申告していれば大丈夫」と思いがちですが、近年の判決がその常識に一石を投じました。令和4年4月19日の最高裁判決は、財産評価基本通達(いわゆる「評価通達」)に基づく相続財産の評価が、場合によっては認められない可能性があることを明示しました。本記事では、その背景と意義、そして実務への影響をじっくり紐解いていきます。
評価通達と「総則6項」の位置づけ
まず大前提として、相続税法22条は「財産は時価で評価する」と定めています。そして、時価の算定方法を具体的に示したものが「財産評価基本通達」です。不動産であれば、土地は路線価、建物は固定資産税評価額をもとに評価するのが原則です。
ところが、この評価通達には「総則6項」という例外規定があります。これは、評価通達による評価が「著しく不適当」と認められる場合には、国税庁長官の指示により、別の合理的な方法で評価するという内容です。つまり、「ルールに従っているだけでは済まされないケースもある」ということなのです。
最高裁が判断した「不動産評価と相続税ゼロ」の事案とは
本件の背景には、次のような事実関係がありました。
被相続人は、亡くなる数年前に高齢でありながら多額の借入れを行い、収益用不動産を立て続けに取得していました。これらの不動産は、路線価・固定資産税評価に基づくと相続税評価額が実勢価格の約1/4程度にとどまり、借入金と相殺すると相続税がゼロになるというものでした。
しかし、課税庁はこれを見逃さず、「評価通達による評価では著しく不適当である」として、鑑定評価額(市場における客観的交換価値)による更正処分を実施。結果、約2億4千万円の相続税を課したのです。
納税者はこれを不服として争いましたが、最終的に最高裁は課税庁の処分を適法と認めました。
最高裁の判断ポイント:二段構えのチェック体制
最高裁は次の2つの視点から課税庁の更正処分を検討しました。
① 相続税法22条に照らして「時価」かどうか
まず、評価通達に基づかない評価であっても、それが相続時点の客観的交換価値(=時価)を超えないのであれば、法22条に反するものではないと判断されました。つまり、鑑定評価額が適正な時価であれば、それを基に課税しても問題ないという考えです。
② 租税法上の「平等原則」に違反していないか
次に、課税庁が特定の納税者だけに通達と異なる評価方法を適用することが平等原則に反しないかが問題になりました。原則として、通達に基づく評価はすべての納税者に平等に適用されるべきです。
しかし、最高裁は「節税を目的とした不動産購入と借入れによって相続税の負担が極端に軽減された場合、画一的な通達評価の適用は租税負担の公平を損なう」と判断。結果として、通達評価に従わず、鑑定評価を用いた課税は平等原則にも違反しないとされました。
総則6項の運用と実務への影響
この判決以降、総則6項の適用を睨んだ調査が現場で増加しています。国税庁は令和4年7月に各国税局へ対応方針を示し、以下の3つの基準を示しました。
- 基準①:他に合理的な評価方法があるか
- 基準②:通達評価額と他の方法による評価額に「著しいかい離」があるか
- 基準③:それでもなお通達評価に従うと「公平に反する合理的理由」があるか
これらを総合的に判断して、通達によらない鑑定評価などが採用される可能性があるのです。
節税対策としての資産構成変更に潜むリスク
相続税対策として、高齢になってからの借入れによる不動産購入は昔からよくある手法です。評価額が下がる一方で、借入れが債務控除できるため、課税価格を圧縮できるからです。
しかし、本件のように、
- 相続直前の購入
- 大規模な借入れ
- 被相続人の高齢
- 相続人が購入直後に不動産を売却
などの状況が重なると、節税目的が強く疑われ、総則6項の適用対象になるリスクが高まります。
マンション評価への影響と新たな実務
令和5年には「マンション通達」も発遣され、区分所有マンションの評価見直しが行われました。全国の75%以上が対象とされ、通達評価額は平均で約1.4倍に見直されています。
しかし、実勢価格とのかい離は依然として大きく、今後も総則6項の適用が残る場面があることに注意が必要です。
さらに、通達評価額が市場価額を「上回る」ケース(地方不動産など)でも、総則6項により納税者に有利な評価方法が認められる可能性があるとされており、これは実務に大きなインパクトを与えています。
実務上の留意点:税理士の視点から
相続税申告に際しては、次のような視点でリスクの有無をチェックすることが重要です。
- 購入時期:相続開始の直前の取得か?
- 購入目的:収益目的か、節税目的が濃厚か?
- 借入金:債務控除される借入額の多寡
- 売却の有無:相続開始後すぐに売却しているか?
上記の要素に加え、総則6項が適用された場合には、鑑定評価額での申告も視野に入れておく必要があります。特に、通達評価額と時価の差が1億円以上ある場合は、調査の対象になる可能性が高まります。
まとめ:通達は万能ではない。「公平」の視点が問われる時代に
評価通達は、あくまで課税庁内部の基準に過ぎず、法的効力があるものではありません。そして、相続税法22条が求めるのは「客観的交換価値としての時価」による課税です。
本判決は、通達による機械的な評価が「公平」に反する場面では、通達を超えて実質的な評価が認められることを明確にした重要な判断です。
相続税対策を検討する際には、節税の効果だけでなく、「実質的な公平性」や「取扱いの平等性」までを見据えた判断が求められる時代に入ったといえるでしょう。
めい税理士事務所では一般社団法人やNPO法人など、非営利法人ならではの会計・税務の悩みに、専門的にお応えします。またマネーフォワードを中心に、クラウド会計の導入から日々の運用まで丁寧にサポートいたします。