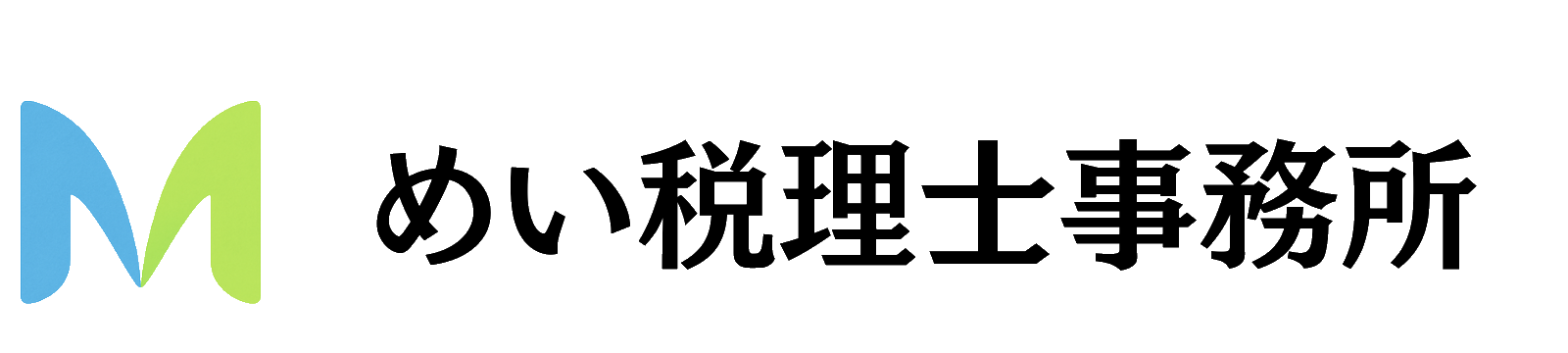Site Menu
輸出取引は消費税がかからない? 知っておきたい「輸出免税」の仕組み
こんにちは。千代田区水道橋の税理士の竹岡悟郎です。今回は輸出取引における消費税についてお伝えしたいと思います。
私たちが日々支払っている消費税。この制度には、実は「輸出」という国際的な取引において特別なルールが設けられています。たとえば、製造業で海外に商品を販売した場合、通常の国内取引とは異なり「消費税がかからない」どころか、「仕入時に支払った消費税が還付される」ケースもあります。
今回は、そんな「輸出免税」について、制度の基本から実務での注意点まで、税理士の視点で分かりやすく解説します。
輸出免税の基本と制度の仕組み
なぜ輸出には消費税がかからないのか?
消費税は、「国内で消費されるモノやサービス」に対して課される税金です。ところが、輸出取引は商品が海外に渡り、日本国内で消費されることがないため、「課税の対象外」とするのが国際的なルールです。これを「国境税調整」といい、輸出品には消費税を課さず、反対に輸入品には消費税を課すことで、国内製品と輸入製品の税負担を公平に保っています。
輸出免税のもう一つの特徴——仕入税額控除と還付
輸出取引が免税であるにもかかわらず、その商品を作るために国内で仕入れた材料やサービスには消費税がかかっています。そこで、事業者は仕入時に支払った消費税を「仕入税額控除」として差し引くことができ、それでも控除しきれない分は「還付金」として戻ってくる仕組みになっています。
つまり、輸出免税取引は、売上に消費税がかからず、仕入にかかった消費税は戻ってくる「二重の優遇」がある制度なのです。
免税対象となる輸出取引とは?
輸出免税の対象となる主な取引
消費税法では、次のような取引を輸出免税の対象としています(消法7条、消令17条)。
- 国内からの輸出として行われる資産の譲渡・貸付け(いわゆる有形資産の輸出)
- 外国貨物(輸入手続前の貨物)の譲渡・貸付け
- 国際旅客・貨物の運送や通信
- 無形資産の譲渡・貸付け(著作権やライセンスなど)
- 役務提供(コンサルティングなど)で非居住者が受益者の場合 など
ただし、「非居住者」であっても、日本に事務所や支店がある相手への役務提供は「居住者」扱いとなり、輸出免税の対象にはなりません。
曖昧になりがちな「輸出」の判定
輸出免税は「国内取引」であることが前提です。たとえば、日本国内で行った取引が「国外取引(不課税)」と判定される場合は、そもそも輸出免税を適用する余地がありません。よって、「これは輸出か?」を判断する前に、まず「これは国内取引か?」をきちんと確認する必要があります。
有形資産の場合は、税関手続き(輸出申告と許可)を通っていれば比較的明確ですが、無形資産や役務提供は判断が難しく、契約書や取引実態に即した判断が重要です。
実務上の留意点:輸出免税は簡単ではない
証明書類の保存が不可欠
輸出免税を受けるには、「輸出であることの証明」が求められます。有形資産であれば、税関が発行する「輸出許可書」の保存が原則です。郵便輸出やEMSの場合には、発送伝票の控えや受領書なども保存対象になります。
これらの書類は、「課税期間終了後2か月を経過した日から7年間」保存しなければなりません(消規5条)。書類の不備があれば、免税の適用が否認されることもあるため注意が必要です。
還付を受けるには確定申告が必要
輸出免税により発生する「仕入税額控除の還付」を受けるには、確定申告を行う必要があります。課税売上がゼロであっても、申告をしない限り還付は受けられません。
特に輸出比率が高い企業は、資金繰りの観点からも課税期間を「1か月」または「3か月」に短縮する制度(消費税課税期間特例)を利用し、定期的に還付申告を行うことも検討されます。
還付加算金や制度悪用への懸念
還付制度は資金繰り上、企業にとってありがたい制度ですが、不正も問題視されています。たとえば、偽の仕入を作って還付を受けるといった事例が過去に摘発されたこともあります。
また、輸出企業が過度に仕入価格を引き下げていた場合、本来の還付目的から逸脱し、還付が「補助金化」してしまうという批判もあります。こうした背景から、国税当局も輸出免税に関しては厳格な審査を行っています。
実際の判定で誤りやすいポイントとは?
「非居住者向け」でも免税にならないケース
たとえば、海外法人にコンサルティング業務を提供した場合でも、その便益(サービスの成果)が日本国内で享受されるのであれば、輸出免税は認められません。また、外国法人であっても日本に支店がある場合は「居住者」とみなされ、こちらも免税対象外になります。
このように、消費税の非居住者は「所得税法の非居住者」とは定義が異なるため、注意が必要です。
名義人に注意——誰が「輸出したのか」
輸出免税の適用を受けるには、「輸出許可書に記載された名義人」=「実際の取引主体」でなければなりません。たとえば、A社が実際に輸出していても、輸出許可書がB社名義であれば、A社は免税を受けられません。ただし、一定の証明手続を行うことで実務的には対応可能なケースもあります。
まとめ:輸出免税は制度の理解と証明がカギ
輸出免税は、国内外の税制バランスを保つために設けられた重要な制度です。しかし、免税だからといって手続が簡単というわけではなく、「輸出取引であることの証明」「非居住者かどうかの判定」「取引の内外判定」など、多くの確認事項があります。
制度を正しく理解し、要件に応じた書類の準備や申告のスケジューリングを行うことが、スムーズな還付申告とリスク回避の第一歩になります。
めい税理士事務所では一般社団法人やNPO法人など、非営利法人ならではの会計・税務の悩みに、専門的にお応えします。またマネーフォワードを中心に、クラウド会計の導入から日々の運用まで丁寧にサポートいたします。