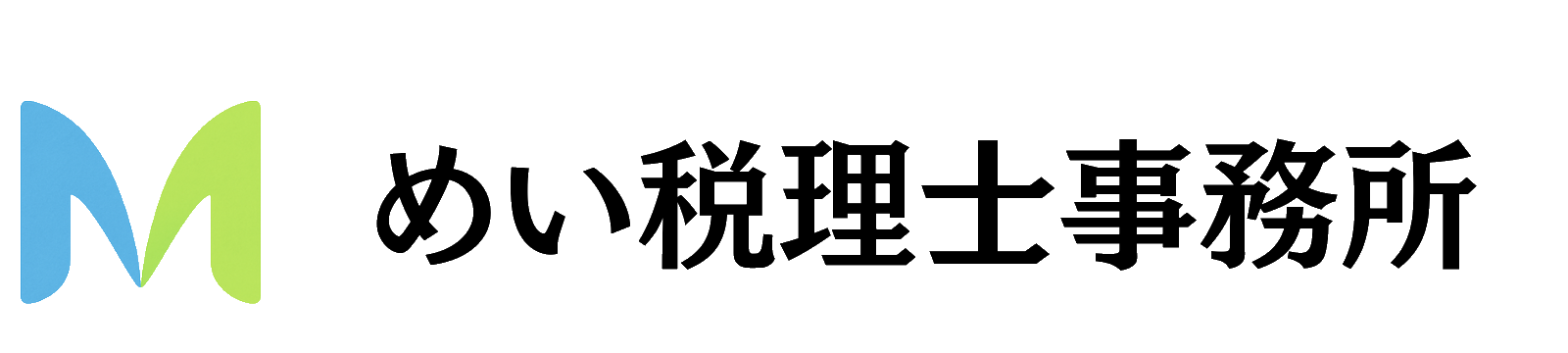Site Menu
公益法人等の収益事業に関する所得計算の基本と実務のポイント
こんにちは。千代田区水道橋の税理士の竹岡悟郎です。今回は公益法人等の収益事業に関する所得計算についてお伝えしたいと思います。
公益法人や一般社団法人、NPO法人などの非営利法人は、「公益性があるから税金がかからない」と思われがちですが、実は一部の活動には法人税が課されることがあります。それが「収益事業」です。今回は、非営利法人が収益事業を行う際に必要な「所得の計算方法」や「会計上のポイント」について、できるだけやさしく、そして実務に役立つかたちで解説します。
収益事業とは? ~どんな活動が該当するのか~
まず、「収益事業」とは何かを明確にしておきましょう。法人税法上の定義では、「継続して事業場を設けて営まれる、政令で定められた34種類の事業」を指します。
①物品販売業 ②不動産販売業 ③金銭貸付業 ④物品貸付業 ⑤不動産貸付業 ⑥製造業 ⑦通信業 ⑧運送業⑨倉庫業 ⑩請負業 ⑪印刷業 ⑫出版業 ⑬写真業 ⑭貸席業 ⑮旅館業 ⑯料理業その他の飲食店業 ⑰終戦業 ⑱代理業 ⑲仲立業 ⑳問屋業 ㉑鉱業 ㉒土石採掘業 ㉓浴場業 ㉔理容業 ㉕美容業 ㉖興行業 ㉗遊技所業 ㉘遊覧所業 ㉙医療保健業 ㉚技芸教授業 ㉛駐車場業 ㉜信用保証暁 ㉝無体財産提供業 ㉞労働者派遣業
非営利法人であっても、これらの事業を行い、対価として金銭などを受け取っていれば、それは「収益事業」に該当し、その収益から得られた所得については法人税が課税されます。
たとえば、一般社団法人がイベントでグッズを販売したり、NPO法人がカフェを運営したりした場合、それが継続的な活動であれば収益事業として課税対象になります。
収益事業の所得計算の基本ルール
公益法人等における法人税の申告は、あくまでも収益事業に限定されます。したがって、収益事業にかかる「収入」「費用」「資産」「負債」などを他の活動としっかり区分して会計処理することが大前提です。
区分経理の基本
- 収益事業に直接かかった費用は、そのまま収益事業の経費に。
- 収益事業以外にかかった費用は非課税の事業に対応。
- **共通の費用(人件費、光熱費など)**は、使用割合・従事割合・収入比など合理的な基準で按分(配賦)します。
内部取引には注意
法人内部での利子や賃料のやりとり(たとえば、収益事業が非収益事業から資産を借りて使用する場合など)については、損金として認められません。あくまでも「実際の外部とのやりとり」が対象です。
特例的な取り扱い ~借入金利子・資産の処分など~
非営利法人特有の事情として、外部からの借入が必要な場合や、共用財産の処理、固定資産の処分など、特例的な会計処理が必要なケースもあります。
借入金利子の扱い
本来、借入金の利子も共通費用として配賦されますが、以下のようなケースでは収益事業の損金にできます。
- 法令上、非収益事業で借入が制限されている場合
- 収益事業を継続・遂行するために必要な借入であることが合理的に説明できる場合
※ただし、故意に所得を減らす目的の借入は認められません。
固定資産の処分益・損
- 通常の売却は収益事業の所得に該当しますが、
- 10年以上保有した固定資産を処分する場合は、キャピタルゲインと見なされ、収益事業の所得に含めなくてよいとされています。
- 収益事業の廃止に伴う資産の処分も、清算とみなされ、原則課税対象外です。
申告書の作成と添付書類のポイント
法人税の申告に際しては、以下のような書類を添付する必要があります。
- 法人全体の貸借対照表・損益計算書(収益事業以外も含む)
- 収益事業部分に限定した損益計算書
収益事業に特化した会計区分が難しい場合には、「区分経理表」などを用いて、合理的に収益事業部分を抽出するのが実務上の対応となります。
実務で求められる「会計上の配慮」
収益事業と非収益事業の「線引き」は、想像以上に繊細です。たとえば以下のようなケースでは判断や処理に迷いが生じがちです。
共用資産の処理
1つの資産(たとえば、車両や建物)を両方の事業で使っている場合、その資産自体は非収益事業に属するものとして処理し、そこから生じる費用(減価償却費、燃料代など)を合理的基準で配分します。
配賦基準の選び方
- 減価償却費 → 使用割合
- 人件費 → 従事割合
- 利子 → 総資産の帳簿価額の比
- 地代家賃 → 面積比
- 電気代 → 電灯の数
それぞれの費用の性質に応じて、配賦基準を柔軟に使い分けることが求められます。
非営利型一般社団法人の注意点
「非営利性が徹底された一般社団法人」も、税制上は公益法人等に該当します。そのため、以下の点に特に注意が必要です。
- 収益事業の有無を明確にし、収益事業部分だけ課税される
- 共通費用・共用資産の区分を徹底する
- 非収益事業に該当する資産(共用車両など)は、あくまで非収益事業に計上。費用は合理的に配分する
また、申告書には法人全体の財務諸表の添付が求められますので、「収益事業だけを切り出した帳簿」では不十分です。
まとめ:公益法人の税務は“分ける”ことが肝心
公益法人や非営利型法人にとって、法人税の課税対象はあくまで「収益事業」に限定されます。しかし、だからといって油断は禁物。収益と費用、資産と負債の「区分経理」がきちんとできていないと、課税誤りのリスクが高まります。
日頃から、収益事業と非収益事業を明確に分け、合理的な配賦ルールを定め、適切な会計処理をしておくことが、正確な申告と安心な運営につながります。特に、実務では細かな例外や特則が多いため、税理士など専門家のアドバイスを受けながら丁寧に対応することが重要です。
めい税理士事務所では一般社団法人やNPO法人など、非営利法人ならではの会計・税務の悩みに、専門的にお応えします。またマネーフォワードを中心に、クラウド会計の導入から日々の運用まで丁寧にサポートいたします。