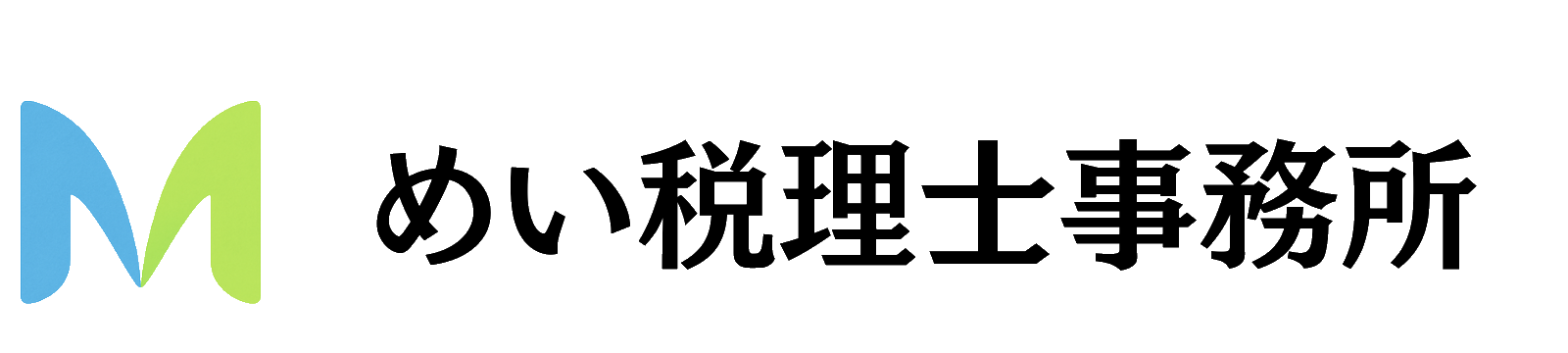Site Menu
関西弁は直りまへん― 東京で働く税理士としてのスタイル
こんにちは。千代田区水道橋のひとり税理士竹岡悟郎です。
東日本大震災の年に神戸から東京に出てきて、もう14年くらい、日常生活はもちろん、お客様との面談の場面でも関西弁で通しています。
よく「東京に来たら標準語に直した方がいいんかな?」となりがちですが、私自身は直す努力はまったくしませんでした。する気もなかったです。
やっぱり不慣れな言葉でしゃべると、噓くさくなっちゃいますし、むしろ自分らしい話し方として残しておいた方が良いと思いまして。
関西以外の地方出身者は方言を抑える?
そういえば、関西以外の地方出身の方は、方言をほとんど出さないようにしているような気がします。気のせいでしょうか。
- ビジネスでは標準語の方が無難だと思われている
- 方言が通じないかもという不安
- 「訛ってる」と言われた経験から抑えるようになった
こうした理由でしょうか。
一方、関西弁は全国的に認知度が高く、お笑い文化やテレビの影響もあって「個性」として受け入れられやすい。
そのため、関西出身者は無理に直さず、そのまま使い続ける人が多いのかもしれません。
さすが傲慢ですね。
関西弁で仕事をするメリット
税理士という仕事は、数字や法律の話を避けて通れません。
どうしても堅い話になりがちですが、関西弁で話すとこんなメリットがあります。
無理やり考えるとですが。
1. 柔らかさと安心感
関西弁には語尾や言い回しに柔らかさがあります。
同じ内容でも、標準語より圧迫感が少なく、相談しやすい雰囲気を作れます。
2. 自然体で信頼を得られる
言葉を無理に直さず、ありのままで話すことで、お客様に「飾らない人」「素直な人」という印象を与えやすいです。
税理士業では、人柄への信頼が契約の決め手になることも多いので、この自然さは強みになります。
3. 会話のきっかけになる
「(関西での)出身はどちらですか?」という雑談が生まれやすく、初対面でも打ち解けやすくなります。
数字や税務の話に入る前のアイスブレイクとしても効果的です。
以上3つのメリットを考えてみましたが、面白くなかったですね。
注意していること
ビジネスの場ですから、あまりに砕けすぎた表現や、関西特有で意味が通じにくい言い回しは避けるようにしています。
例えば、「なおす」という言葉を「片づける」という意味で使うと、関東では誤解されることがあります。
まあ今はもうないですかね。
こうした点だけ気をつければ、特段マイナスになることはほとんどありません。
言葉は自分らしさの一部
東京で関西弁を使うことは、私にとって「ただの習慣」ではなく「自分らしさの表れ」でもあります。
税理士という仕事は、信頼関係のうえに成り立っています。
その信頼を築くために、無理に標準語に合わせるより、自分の自然な言葉でお客様と向き合うほうが、結果的に良い関係を作れると感じています。
東京で働く関西弁の税理士――。
それは私にとって、ちょっとした個性であり、仕事の強みでもあるのです。
なんてな。
めい税理士事務所では一般社団法人やNPO法人など、非営利法人ならではの会計・税務の悩みに、専門的にお応えします。またマネーフォワードを中心に、クラウド会計の導入から日々の運用まで丁寧にサポートいたします。