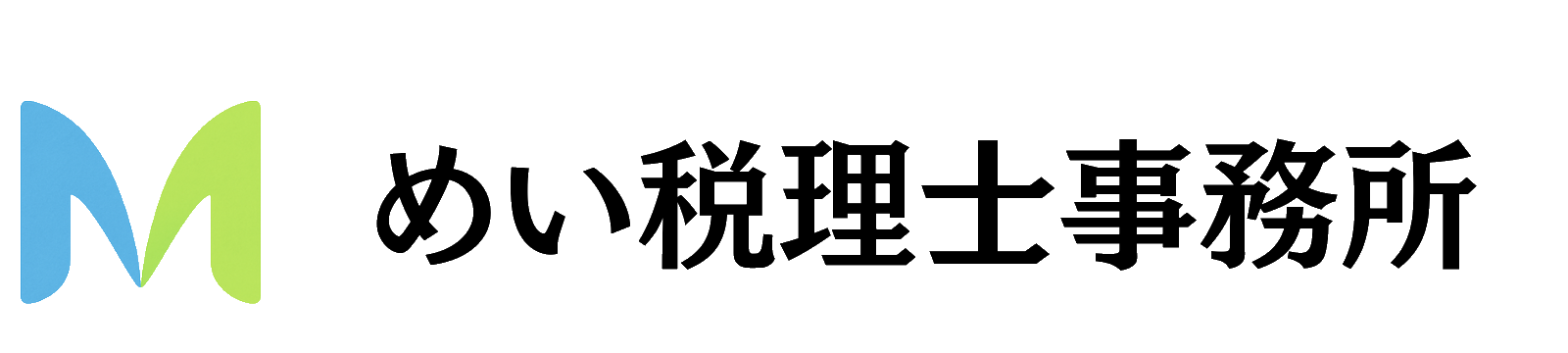Site Menu
税理士に対する顧問料、その価値をどう考えるか
こんにちは。千代田区水道橋のひとり税理士竹岡悟郎です。今回は税理士に対する顧問料について、お話したいと思います。
税理士の顧問料の相場は、規模にもよりますが、平均的に月々3万円くらいが相場のようです。しかしながら・・・
「税理士に毎月3万円払うのは高い」
「ほとんど相談もしないのに、なぜこんなに払っているんだろう」
小規模事業者の方からは、そんな声を聞くことがあります。
たしかに、日々の経理作業や申告がスムーズに進んでいて、特別なトラブルもない状態であれば、「この顧問料って本当に必要?」と疑問に思うのは自然な感覚です。
そんな「顧問料」についてのお話です。
経営パートナーの対価としての顧問料
たとえば、次のような場面、
- 「この取引って、消費税かかるのかな?」
- 「新しく従業員を雇ったけど、社会保険の手続きってどうするんだろう?」
- 「税務署から何か届いたけど、どう対応すればいいの?」
こうした疑問や不安が生まれたとき、「すぐに相談できる人がいる」というだけで、経営者は安心できます。
さらに、制度や税制の知識がなければ見落としがちなリスクを、税理士が早い段階で指摘し、未然に防ぐことができます。
つまり、顧問料は「帳簿や申告書の作成料」ではなく、経営の道しるべとして伴走するための経営のパートナー料としての側面もあるではないかと。
顧問先が感じる「作業の対価」とのズレ
しかし現実には、顧問料を「記帳や申告の作業に対する報酬」と考えている顧客も少なくありません。
特に、相談頻度が低く、自計化も進んでいる小規模事業者ほど、
- 「仕訳は自分で入力している」
- 「毎月の会話はほとんどない」
- 「年に1回の申告だけ頼んでいる」
といった状況になり、その割に高いと感じるのも無理はないのかもしれません。というか普通はそう感じると思います。ハッキリと形あるものを提供を受けないとっていう。
この「価値の感じ方」のギャップは、税理士であれば少なからず感じることが多いのではないでしょうか。
目に見えるものでも見えないものでも価値を伝える
どうすれば顧問料の価値を感じてもらえるのか。
それには、税理士が目に見えるものでも見えないものでも、何ができるか価値あるものしっかり伝えることが必要だと思います。
- 毎月、会計データをチェックし、税務リスクがないことや、企業の財務状況をリアルタイムでお伝えする
- 年度途中の利益を把握して、決算前の節税対策の提案や、経営判断のための材料を提供する
こうした業務は、日々の中で当たり前のように行っていることかもしれませんが、意識して伝えていくことが大切ではないでしょうか。
定期的なレポートや面談の場で、わかりやすく説明することで、「なるほど、そういうことまで見てくれているんだ」と納得してもらえるようになります。
メニューをしっかり作る
また、顧客からしたら税理士事務所では「何をしてもらえるのか、できないのか」をしっかり明記することで、その顧問料が高いか安いかを判断してもらうのに大事なのかなとも思います。サービス内容と報酬の対応関係がわかりやすくなるかと。
「やらないこと」を明確にするのは一見マイナスに見えますが、逆に言えば「専門性を活かしたサービスに集中している」という差別化の武器になります。
付加価値の積み重ねが「納得感」になる
それでも、どうしても「月額3万円」という金額に対して“もったいない”と感じる方もいるでしょう。
その場合にも、
- 簡単な経営コメントを添えた会計レポートを渡す
- LINEやチャットで気軽に質問できる仕組みを整える
- キャッシュフロー分析や資金繰りのアドバイスを提供する
このような形で、大げさなことをしなくても、お客様にとってなにか形あるものを提供することも、最終的には信頼につながり、顧問料についても納得していただけるのではないでしょうか。
めい税理士事務所では一般社団法人やNPO法人など、非営利法人ならではの会計・税務の悩みに、専門的にお応えします。またマネーフォワードを中心に、クラウド会計の導入から日々の運用まで丁寧にサポートいたします。